【JTA設立10周年記念特別座談会】「2015年2団体統合へ あの頃あの時」

日本機械工具工業会(以下JTA)が本年設立10周年を迎えるにあたり6月2日(月)に東京マリオットホテル(東京都品川区)でJTA設立10周年記念特別座談会『2015年2団体統合へ あの頃あの時』を開いた。この企画は統合当時の出来事を後世に残す狙いがある。
日本機械工具工業会は2015年に超硬工具協会と日本工具工業会が統合して設立された団体で、日本機械工具工業会としての歴史は10年を迎えるが、両団体が設立されたのは1948年。実質は77年という歴史がある。
〈出席者〉
・増田照彦 旧日本工具工業会・旧超硬工具協会理事長
・堀 功 旧日本工具工業会理事長
・石川則男 旧日本工具工業会理事長,日本機械工具工業会元会長
・牛島 望 旧超硬工具協会理事,日本機械工具工業会元会長
〈司会〉
・八角 秀 ニュースダイジェスト社 代表取締役社長
〈オブザーバー〉
・イワタツール 代表取締役社長 岩田昌尚(元統合推進委員)
・インダストリー・ジャパン 社長 那須直美(筆者)

八角 統合に向けて増田さんは大きな役割を果たされた。当時を振り返って思うことは?
増田 2012年と13年に日本工具工業会の会長、14年と15年には超硬工具協会の理事長に就任した。2団体とも切削工具について真面目に取り組んでおり、統合に向け、まずは、気楽に「一緒になればいい」と思い描いた。私が日本工具工業会の会長に就任する前に『MYツール』が発刊されたが、業界の情報が豊富で、当時、彌満和製作所の細島さん(MYツール編集委員)は私の知恵袋のような存在だった。そのときから、業界の伝統と風格が、この業界を狭い世界にしているのだろうと、これを解き放った方が良いのではないか、と感じていた。また、当時のメンバーで、寺島さん(東鋼社長)、田野井さん(田野井製作所社長)さん、岩田さん(イワタツール社長)のような存在をこの中で閉じ込めておくのは勿体ないとも思っていた。一方、超硬工具協会は大企業が占めており、どちらかというとサラリーマン社長が多い。元々感じていたことだが、工具メーカーは家族経営のほうが良い。日本工具工業会が持っている家族経営の良さを超硬工具協会の皆様にも知って頂きたいという思いがあった。
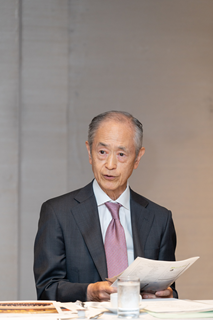
八角 堀さんはハイスのトップとしてどのように感じていたか。
堀 私が工具業界に携わったのは1987年で38年ほど経つが、当時のドリルはハイスが主流だった。コベルコが超硬ドリル、ミラクルドリルを出したのは94年か95年頃だったと思う。その頃から日本工具工業会のメンバーも超硬ドリルや超硬エンドミルが主流になり、ハイスも超硬も垣根がない状態だったので、別々の工業会でいる必要がないだろうという思いは自然に出てきたと思う。残ったのはタップ、ブローチ、歯切工具などでドリルもエンドミルも超硬の方が圧倒的に出荷額は大きくなっていた。自然に世の中の加工の流れに沿って統合の方向に向いて行くのは自明の理。過去に2度ほど統合の話が出たものの、結局実現せずにいたのだが、統合のきっかけは、増田さんが両団体のトップになられたことが非常に大きいと思う。

牛島 統合の話は、80年代末に1度、90年代後半から20年ぐらいにかけて2度あった。この時、超硬サイドではメリットの創出について議論が起こったが、正直言うと、あまり興味を示さない企業が多かったようだ。古い話だが、戦時中から超硬3社は陸軍にて強烈に指導され、一方、ハイスは海軍指導で、その頃からどうも水と油のような関係があったのかもしれない(笑)。2013年に京都で開催されたWCTCではサンドビックの藤井さん、増田さん、当時日立ツール(現MOLDINO)の田中さんにはご尽力いただき、ここで機運が盛り上がったと思う。
石川 増田さんが両団体のトップについたことは非常に大きかった。統合に関しては超硬工具協会のほうはあまり興味がなく、一方、日本工具工業会も大手の多い超硬工具協会と一緒になることを良く思わない方もいた。リーダーシップが強すぎても難しいし、リーダーシップがないと何も起きない。



