微細加工機の新たな基準をつくりあげた碌々産業の挑戦!
 碌々産業(社長=海藤 満氏 本社:東京都港区高輪4-23-5)が革新的マシン『MEGA』により微細加工分野を切り開いたのは1996年。今では微細加工マシンといえば碌々産業を思い浮かべるユーザーも多い。
碌々産業(社長=海藤 満氏 本社:東京都港区高輪4-23-5)が革新的マシン『MEGA』により微細加工分野を切り開いたのは1996年。今では微細加工マシンといえば碌々産業を思い浮かべるユーザーも多い。
「加工機そのものの進化に加え、最適なソフトウェア、最適な工具、最適な加工環境を含めた“四位一体”の考え方で、一貫して微細加工のレベルアップを追求してきました。現在、われわれは微細加工機のリーディングカンパニーの誇りをかけて“微細加工機の新しい基準”を世界に発信していきます」と話す海藤社長。
同社の静岡工場では究極の実加工精度を追求するマシンがつくられている―――。
玄人好みの超微細加工機と噂の『Android』は、まさに碌々産業が渾身の力を込めて開発したマシンであった。
徹底した細部へのこだわり―― 常温23±0.5℃制御完全恒温精密組立工場「Area23」

「Area23」は省コストの水利用で環境に優しい安定した空調システムがある

この中心部は「Area23」と呼ばれ、碌々産業の“精鋭特殊部隊”が所属する常温23±0.5℃に完全制御された恒温精密工場である。出入り口は全て2重化しており、風除室も換気で外部からの悪影響を最小にしている。入室人数も制限され、毎秒1mの速度のもと水と湯で温度管理された空気のシャワーが天井から降り注ぐ。これらをシステムによって知的にコントロールしている箇所があり、全てがPCでデータ化されている。
マシンをつくる環境がしっかりしていれば、精度が良くなり剛性はより高くなる。河村長治取締役技術本部長は、「鉄は1℃変われば10μm/m変化します。世の中に“変化しないもの”は存在しません。万が一、機械のつくり込み過程でトラブルがあった場合、特別な温度環境があったかどうかを調べられるようになっています」と説明をしてくれた。

加工機の挙動を「見える化」し、きめ細やかな補正で究極の加工精度をユーザーに提供するマシンだ。
他社に先駆けて微細加工機を世に提案した碌々産業が先駆者として挙げているのが“操る悦び”。
海藤社長は操る悦びについて、「ユーザーさんが積極的にマシンを操ることに悦びを感じてくれる機械をつくるというコンセプトのもと、この『Android』はつくられました。操る悦びとは、すなわち、オペレータがマシンのクセを掴み、自由自在に操り、究極の実加工精度を追求できることです」と話す。しかも驚くことにこのマシンは90項目以上におよぶ同社の人気機種である「MEGA」の改善点を網羅している。この90項目は、ユーザーを訪ね歩いて得たヒントによるものだ。
「たとえば窓の裏を拭けるようにするなど、掃除がしやすいのも機械を使う人にとっては大切な要素。お陰様で現在、『Android』は競合機を脅かスペックとなっています」(海藤社長)
「実加工精度1μm以下を達成せよ!」 加工機の挙動を“見える化”し、“熟練のワザ”で補正

開発プロジェクトを立ち上げ、振動を極限まで抑制した――。
高速スピンドルの振れ精度と熱変位までも徹底的に抑えてきた――。
ところが、個々の微少な変化が、安定した±1μm以内の加工が困難だった。これを克服するためには、機械稼働に伴う挙動をオペレータが掴みその微小変位を補正し加工を行う必要がある。そのために同社が着手したことは、「加工機の挙動を“見える化”」だった。

実加工精度1μm以下の達成のために、着手したのはセミオートマ化だった。微細加工をこなすためには工具のセッティングから、ワークをどう固定するか・・・も課題だった。
「機械のクセを掴んで自由に操ることができるのは日本人が得意の分野。これはかつて汎用機を駆使し、究極の精度を追求した“匠の技”の再現にほかならない」(海藤社長)
海藤社長は『Android』を「高精度実現に対するオペレータの意図を忠実に反映できる人造人間」だとしている。製品名にはそういった思い入れがあるのだ。
海藤社長はいう。
「われわれは高精度、微細加工を実現するために、最適な機械、最適なソフトウェア、最適な工具、最適な環境を申し上げていたが、これらに加え、大切な要素が他にもあることに気付いたのです。それはオペレータです。人なのです。機械を自由自在に操る人が大切なのです。オペレータの意志が忠実に機械に反映されること、これがなくては究極の実加工精度を追求することはできません」

鋳物の存在感と碌々らしさ

ショールームは機械の展示のほか、テストカットを行っている。

総加工時間は1個につき、22分20秒。16個の連続加工でも、真円度、同心度、面粗度、径精度、どれをとっても全て1μm以内の数値を叩きだしている。
同社は穴あけにも強い。
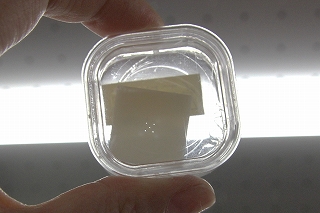
被削材材質はジルコニア(Z-201N)20×20×2(0.5貫通)[㎜]。使用工具はイワタツールのφ0.1ダイヤモンド電着砥石(粒度#1000)。加工時間は7.5分/穴。
同社では「ZYGO New Vlew7100」という面粗度を図る装置も完備している。これは非接触で測定できるもので、微細なLED等の金型など、触れると精度が変わってしまうようなものでも安心して測定できる優れモノだ。
さて、加工に携わる多くの皆さまが「碌々産業」の碌々とはなんだろう? と感じたと思う。
碌々産業の歴史は古く、1903(明治36)年にさかのぼる。初代社長野田正一が東京銀座で「碌々商店」を創業し、機械工具類の輸入販売を開始したのがはじまりである。社名の由来は、「甲等碌々、所謂因人、成事者也」(こうらろくろく いわゆるひとによりて ことをなすものなり)という漢詩の一節にある。
『個人の力と個性が集結し、そして刺激し合い、初めて大きな力と成り得る』
これには柔軟な発想と大胆な行動力への大きな期待も込められていると聞いた。
海藤社長は、「100年の時を経た今も、これからもこの精神と社風は受け継がれています。明治維新の産業復興期、戦争、需要拡大の高度成長期でも常に貫いた企業精神は「信用」と「堅実」でした。規模拡大よりもお客様のニーズに技術で挑む姿勢は今も変わりません」としめくくった。



