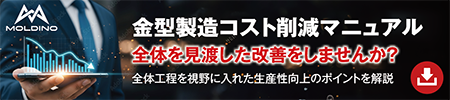「機電再融合の流れは注目しなければならない環境変化と認識」 日本機械工業連合会が賀詞交歓会を開く
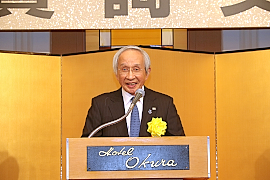
2012年12月2安倍内閣が発足して3年間が経過した。わが国経済は、アベノミクス効果のもとで着実な回復を続けてきた。リーマンショック後6000円台にまで落ち込んだ株価も大幅な上昇を示し、企業体力の回復と雇用・所得の増加、研究開発やM&Aを含む企業の着実な投資拡大の好循環が生まれつつあるといって良いと思う。
かつて六重苦といわれた超円高、自由貿易協定締結の遅れ、世界一高い法人税率などの課題に関して、円安への反転、TPP大筋合意、そして税制中立という考え方が随伴措置とはいえ、法人実効税率のドイツ並みの29%台への引き下げ、地球温暖化にかかるCOP21における米国や中国等の参加した形でのプレッジ・アンド・レビュー方式への転換の実現と、これに先行してのエネルギー・ミックスをしっかり踏まえた約束草案の提出など、総理のリーダシップと担当大臣をはじめとする関係省庁の交渉力や見識の発揮によって、ビジネス環境の改善が大きく図られつつあると考えている。
目を今後に転じると、消費税の再引き上げが来年4月に控える中で、今年こそ、わが国経済を中長期の成長軌道にしっかりと乗せていく年としなければならないと痛感している。政府はアベノミクスの第二ステージとして、新三本の矢をかかげ、人口減少社会という現実に向き合った成長戦略として社会政策的ともいうべき経済政策、子育て支援、社会保障を第二、第三の矢としてかかげるとともに、名目GDP600兆円の2020年頃の達成を目指した希望を生み出す強い経済を第一の矢として位置付け、グローバル・バリューチェーンの構築、イノベーション・ナショナルシステムの構築、IoT・ビッグデータ・ロボット・人工知能による変革等を重視し、こうした課題について継続的な取組を進めようとされている。これらのいずれの課題をとってみても、政府の政策展開だけでは達成不可能であり、機械産業に横串を入れた組織体である日機連としてもこうした時代の動向を見据え、クォリティの高い活動を心がけていきたい。
昨年の賀詞交歓会において私は世界的な製造業再評価の動きについて、機械と電気・電子の機電再融合とでもいうべき潮流の中で、機、電、を横断する組織である日機連としてもこうした流れに対して積極的に取り組んでいきたいという趣旨を申し上げた。その後、政府のイニシアティブのもとでロボット新戦略が取りまとめられ、5月にはこれを受けて日機連が事務局を引き受け、IoT時代に即応したロボット新戦略の推進役としてロボット革命イニシアティブ協議会の発足をみた。その後の進展だが、226の会員の賛同を得て立ち上がったこの協議会は、現在では360を超えるところまで増加し、さらに拡大中である。各ワーキンググループも、毎回多数の企業等の参加のもと回を重ねると共に、議論も活発化し、多くの前向きの提案が会員からなされるなど、組織的なプラットフォームの形成の段階から次のステージに移行する段階を迎えつつあるように感じている。この分野の世界標準をリードすることが必須であり、そのためには会員の皆様、政府のご支援をさらにお願い申し上げる次第である。
機電再融合の流れは、機械産業の人材育成や確保の面においても注目しなければならない環境変化と認識しており、今後は日機連本体とロボット革命イニシアティブ協議会事務局が連携して政府のサポートもいただきながら、機電再融合時代の人材育成・確保のあり方について、検討を深めていきたい。また、今年は日機連本体で経産省と共にこれまで進めていたロボット大賞事業の拡充を図る年である。産業用ロボット以外の分野を含めた開発・普及の促進に向けて、積極的に取り組んでいく。
足元の景気動向は中国を始め新興諸国の景気減速など世界経済の下振れリスクが高まるなか、一進一退ともいわれているが、私どもが47の機械工業団体の協力を得て、去る11月にまとめた機械工業生産額見通しの改訂調査では、平成27年度の国内機械生産額は、当初見通しの前年度比2.6%増から0.7%情報修整の前年度比プラス3.3%という結果が出た。これは一部業種の下期を中心とした上方修正が背景となっているが、私どもとしては、この見通しが是非とも現実のものとなり、わが国経済全体としても今下期に着実な回復の動きを示すことを強く期待している。
「今年は行動をおこす年」

伊藤源嗣副会長(IHI相談役)の乾杯の発声で開宴した。