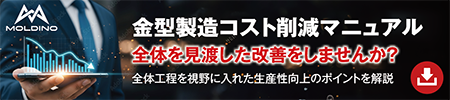台湾TMTS展が6年ぶり単独開催 7万人が来場、オンライン展には11万人
今なお続く新規参入

中国市場の動向に大きく左右される台湾の工作機械業界だが、日本にはない強みもある。新たな工作機械メーカーが日々生まれていることだ。過去のTMTSやTIMTOSでは見たことがない、知らないメーカーが、立派な装飾の小間に、デザイン性に優れた工作機械を並べている。今回のTMTSでも、そんなメーカーが数多く見られた。
「シグマ」ブランドで大形MCを生産する新穎機械工業は2000年、「カンプロ」ブランドで複合旋盤を生産する凱柏精密機械は03年と、創業から20年ほどの若いメーカーだ。逆に1950年代に創業した毅徳機械は一時業績が低迷したものの、90年代に「イーテック」ブランドで米国での販売を強化し、勢いを取り戻しつつある。
グループ化も強みの一つだろう。先に紹介した程泰機械グループは2013年にMCメーカーのエクストロンを傘下に組み入れ、グループとしての強みを生かしている。FFGは傘下の池貝を通じて新日本工機を買収し、再建の途上にある。
逆に、日本と同様に、人材不足の悩みも抱えている。開幕日に開かれたTMBAの外国メディア向けの記者会見で「台湾の製造業ではTSMC(台湾積体電路製造)のひとり勝ちだ」(陳理事長)と世界最大の半導体EMS企業の人気ぶりをやっかむ場面もみられた。少子化とそれに端を発した労働力人口の減少に悩む姿は、日本と同じだ。

TMBAは若い人材へのPRを続けている。TMTSの会場には驚くほど多くの大学生や工業高校の生徒の姿が見られた。TMBAは学生の来場者数を発表しないが、これほど多くの学生を目にする展示会はほかにない。
台湾の工作機械業界で気になる点は、近年急速にドイツとの関係を深めていることだ。2011年にドイツのハノーバーメッセで発表した「インダストリー(I)4.0」を受け、同年のハノーファー・メッセで表舞台に取り上げられて以降、TIMTOS2015やTMTS2016あたりから台湾の工作機械業界との関係を深めている。TMTSが開催されてきた台中は、国策の「スマートシティー構築」実現の場として取り組んできた。通信網や設備などのインフラ整備を行政が、機器やソフトウエアをドイツ企業がそれぞれ担う図式だ。スマートシティー構築に取り組んだ当時の台中市長は、開会式でもあいさつした林佳龍総統府秘書長だ。
中国で稼働するEMSの多くは台湾系企業で、米中両国の関係から、今後EMSの工場を別の国に移設するとみられる。当面は生産設備を移設しても、次の生産能力の増強時には、EMSはドイツ企業をパートナーとして選ぶのが自然とみるべきだろう。米国各地で建設が進むEMSの最新工場では、多くのドイツ製品が導入されているとみて間違いない。最新のNCを調達できる台湾側と、台湾との良好な関係を後ろ盾に、中国と米国での商機を逃したくないドイツとの親密ぶりを、ただ微笑ましく見ているだけでいいのだろうか。
台中での新展示会場の建設が遅れており、次回のTMTS2026は2026年3月に、再び台北南港展示センターで開催される。次回までにどれほど、製造の現場でDXとGXでの持続可能な未来が実現されているのか興味深い。
なお、TMTS2024閉幕から3日後の4月3日午前、台湾東部の花蓮県沖を震源とするマグニチュード7.2の地震が発生し死傷者も出た。亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに、被害に遭われた全ての方にお見舞い申し上げたい。
■是州煩太(これす・ぼんた)
 生まれも育ちも尾張なごや。風に吹かれて東へ西へ、雨に打たれて南へ北へ、星を求めて海へ山へと向かうオプチミスト。政治や経済、社会や文化、スポーツなどの華やかな舞台とは縁遠く、物流やものづくりの世界をのぞき見るつもりが抜けられなくなり今に至り裏方を生きる。大の乗り物好きで、潜水艦にこそ乗り損ねたものの潜水艦を追いかける哨戒機に乗り、なんとかと煙は高いところへとばかりに飛行船に乗ったのがプチ自慢。日本丸と海王丸の甲板をヤシの実で磨き、世界各国の貨物船の食堂でメシをごちそうになったのもいい思い出。写真は撮るけど撮られるのは嫌い。座右の銘は「すきなことはやっておく」。
生まれも育ちも尾張なごや。風に吹かれて東へ西へ、雨に打たれて南へ北へ、星を求めて海へ山へと向かうオプチミスト。政治や経済、社会や文化、スポーツなどの華やかな舞台とは縁遠く、物流やものづくりの世界をのぞき見るつもりが抜けられなくなり今に至り裏方を生きる。大の乗り物好きで、潜水艦にこそ乗り損ねたものの潜水艦を追いかける哨戒機に乗り、なんとかと煙は高いところへとばかりに飛行船に乗ったのがプチ自慢。日本丸と海王丸の甲板をヤシの実で磨き、世界各国の貨物船の食堂でメシをごちそうになったのもいい思い出。写真は撮るけど撮られるのは嫌い。座右の銘は「すきなことはやっておく」。