ニュース
セコ・ツールズが新しい T 刃先処理サイアロンセラミックチップを追加
 セコ・ツールズは、Secomax™ CS100 サイアロンセラミック材種に T 刃先処理チップをこのほど追加し、シリーズの粗加工と中仕上げ機能を強化した。新しいチップは快削で極めて鋭利な形状が特長で、不安定な条件でもニッケルベースの超合金加工を安定して加工する。
セコ・ツールズは、Secomax™ CS100 サイアロンセラミック材種に T 刃先処理チップをこのほど追加し、シリーズの粗加工と中仕上げ機能を強化した。新しいチップは快削で極めて鋭利な形状が特長で、不安定な条件でもニッケルベースの超合金加工を安定して加工する。
切削抵抗を抑えながら、厳しい公差が要求される旋削用途にT 刃先(面取り)の CS100 チップは、幅 0.05 ~ 0.1mm までの 20˚ 面取りに使用できる。これらのチップに鋭利なネガティブ強化刃先を取り付けると、加工機械の設定や被削材に負荷の多い、高い切削力と圧力を一部吸収、その結果、特に薄肉壁コンポーネントで被削材の変形リスクが排除されるほか、工具寿命を縮め、表面仕上げに悪影響を及ぼす過剰な振動が軽減される。また、T 刃先処理チップは、高い剛性と安定性がある加工条件において高い切削抵抗に対応するよう設計された従来の S 刃先(面取り、ホーニング)の CS100 製品にない特長を補間している。
VeroSoftwareグループがエンジニアリング3Dコミュニケーター『PartXplore』をリリース
統合型CAD/CAM/CAEソリューション「VISI」、Automatic CAD/CAMソリューション「WorkNC」、ミリング・複合・旋盤加工向けCAD/CAMソリューション「Edgecam」等の開発販売を手掛ける英国Vero SoftwareLimitedのグループ子会社の日本法人(東京都港区)は、新製品のエンジニアリング3Dコミュニケーター『PartXplore(パートエクスプロア)』の出荷を開始した。 主な特長は、①簡単な操作性、②豊富なマルチCADインポーターを標準搭載、③高速表示・高精度測定、④3Dモデルへ注釈・ラベル配置、時間軸によるアニメーション作成、配布用クライアントビューワ作成。 なお、同社では、4月19日(火)より名古屋にて開催される「設計・製造ソリューション展」および4月20日(水)より大阪にて開催される「INTERMOLD2016」にて初披露する。
コマツが大型油圧ショベル「PC300(LC)-11/PC350(LC)-11」、大型ハイブリッド油圧ショベル「HB335(LC)-3/HB365(LC)-3」を新発売

新発売の8機種は、NOx(窒素酸化物)とPM(粒子状物質)の排出量を大幅に低減し、特定特殊自動車排出ガス2014年基準の排出ガス規制をクリアした新世代エンジンを新たに搭載している。特に「HB335-3(LC)/HB365(LC)-3」は、これまでコマツが20トンクラスのハイブリッド油圧ショベルで蓄積してきたノウハウと技術を活かした系列拡大商品であり、新たにエンジン・油圧・ハイブリッドシステムのトータル電子制御とファンクラッチシステムを採用したことで、従来標準機の作業性能はそのままに、燃料消費量を当社従来標準機に比べ22%と大幅に低減した。また30トンクラスでは業界で初めて超低騒音型建設機械の基準値をクリアしている。
8機種ともに、国内の販売機種では初めてKomVision(一般建機用周囲監視システム)を標準装備するとともに、オートアイドルストップ、レバーニュートラル検知、オペレーター識別機能等を追加している。新車購入時に自動的に付帯されるパワーラインの保証延長と無償メンテナンスを取り入れたサービスプログラム「KOMATSU CARE(コマツ・ケア)」の提供により、トータルライフサイクルコストの低減と長時間稼働に貢献する。
〈ロボット〉 2015年10月~12月期(会員ベース)及び年間統計 ロボット工業会
ロボット工業会がまとめた「「ロボット統計受注・生産・出荷実績(会員ベース)2015年10~12 月期」及び年間統計2015年1~12 月は次のとおりとなった。なお、同会の月別統計調査を基に作成したもので、同会の正会員及び賛助会員対象企業33 社のうち、回答企業33 社による実績である(サービスロボットは調査対象外)。1.受注について(10~12月期) 受注台数は、対前年同期比で、+8.6%の34,417 台となり、2四半期ぶりにプラスに転じた。また、受注額では、同+8.9%の1,307 億円と、10四半期連続のプラス成長となった。(年間) 受注台数は、対前年比で、+6.5%の138,319 台となり過去最高実績となった。また、 受注額では、同+10.4%の5,446 億円と各々3年連続のプラス成長となった。2.生産について(10~12月期) 生産台数は、対前年同期比、+9.2%の32,999 台となり、10四半期連続でプラス成長。生産額では、同+8.4%の1,246 億円となり、2四半期ぶりにプラスに転じた。(年間) 生産台数は、対前年比で+8.7%の138,434 台となり過去最高実績となった。 生産額では、同+8.0%の5,321 億円となり(資料3)、各々2年連続でプラス成長となった。 昨年2015 年(会員+非会員)の年間生産額(出荷額)は、輸出は円安を背景に海外需要が拡大し、国内は生産性向上設備投資促進税制などの政策により設備投資が増加したことで、対前年比で約6%増の6,300 億円となる見込み。 また、今年2016 年(会員+非会員)の年間生産額(出荷額)は、引き続き国内での需要増に加え、米国での更なる景気拡大と製造業回帰による堅調な伸び、中国での減速経済の中にあっても高い自動化投資意欲、さらに欧米におけるインダストリー4.0 などIoTを通じた産業用ロボットへの関心の高まりなど、今年も海外需要の拡大が期待され、対前年比で約6%増の6,700 億円となる見通し。3.出荷について 国内は主要ユーザーである自動車産業向けと電気機械産業向けが年間を通じて好調であった。 海外市場で見ると、中国向けは年前半こそ好調であったが、景気減速の影響から徐々に需要は減速したものの、米国向けは堅調に推移し、欧州向けは前年の好調をさらに上回る実績となった。(10~12月期) 総出荷台数は、対前年同期比で+12.5%の34,237 台と、10四半期連続のプラス成長となった。 総出荷額では、同+11.1%の1,289 億円となり、9四半期連続のプラス成長となった。 国内出荷台数は同+19.8%の8,212 台、国内出荷額では同+26.7%の381 億円となり、各々9四半期連続のプラス成長となった。 輸出台数は同+10.4%の26,025 台となり、10四半期連続でプラス成長となった。輸出額は同+5.6%の907 億円となり、2四半期ぶりのプラスに転じた。(年間) 総出荷台数は対前年比+9.3%の139,363 台と、過去最高実績となった。 総出荷額では、同+8.9%の5,284 億円となり、各々2年連続のプラス成長となった。 国内出荷台数は同+13.5%の32,483 台、国内出荷額は同+20.9%の1,518 億円となり、各々2年連続のプラス成長となった。 輸出台数は同+8.1%の106,880 台と、3年連続でプラス成長になるとともに過去最高実績となった。 輸出額は、同+4.7%の3,766 億円となり、2年連続でプラス成長となった。3.1国内出荷内訳(10~12月期) 自動車産業向けは、対前年同期比で+32.9%の2,757 台となり、3四半期ぶりにプラスに転じた。出荷額は、同+41.3%の121 億円となり、2四半期連続でプラス成長となった。電子・電気機械産業向けは、対前年同期比で、+20.4%の2,516 台と、10四半期連続のプラス成長となった。出荷額は、同+21.0%の124 億円となり、2四半期ぶりにプラスに転じた。一般組立用や半導体用(ウェハ搬送)、マテハン用が好調であった。(年間) 自動車産業向けは、対前年比で、+6.9%の10,731 台となり、2年連続でプラス成長となった。 出荷額は、同+15.0%の477 億円となり、3年連続でプラス成長となった。 電子・電気機械産業向けは、対前年比で+32.1%の10,315 台と、2年連続でプラス成長となった。出荷額は、同+22.6%の501 億円となり、4年ぶりにプラスに転じた。 ほぼ全用途が好調であった。3.2 輸出内訳(10~12月期) 溶接用は、対前年同期比で▲7.5%の8,723 台となり、10四半期ぶりにマイナスに転じたものの、出荷額では、同+3.6%の240 億円と、10四半期連続のプラス成長となった。 欧州は非常に好調であったものの、米国、中国向けに伸び悩みが見られた。 電子部品実装用は、同▲13.3%の1,597 台、出荷額は同▲12.0%の271 億円となり、各々2四半期連続でマイナス成長となった。電機向けの主要用途である電子部品実装用は、米国、中国向けで大きく減速、欧州向けも前年並みとなった。(年間) 溶接用は、対前年比で▲0.5%の35,008 台となり、3年連続でマイナス成長となったものの、出荷額では、同+4.8%の925 億円と、2年連続のプラス成長となった。 欧州は非常に好調であったものの、米国、中国向けは前年並みとなった。 電子部品実装用は同▲6.7%の8,097 台、出荷額は同▲0.4%の1,321 億円となり、各々2年ぶりにマイナスに転じた。 電機向けの主要用途である電子部品実装用は、欧米向けでは好調であったが、マーケットの中心となる中国向けで年後半から需要が失速した。 輸出は、欧米向けの需要好調であったのに対し、中国向けは景気減速の影響を受け、ロボット需要は低迷したが、自動化投資への意欲は依然高いことから今後の需要回復が期待される。
「機電再融合の流れは注目しなければならない環境変化と認識」 日本機械工業連合会が賀詞交歓会を開く
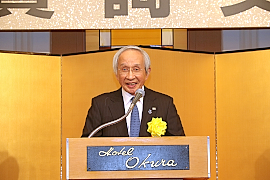
2012年12月2安倍内閣が発足して3年間が経過した。わが国経済は、アベノミクス効果のもとで着実な回復を続けてきた。リーマンショック後6000円台にまで落ち込んだ株価も大幅な上昇を示し、企業体力の回復と雇用・所得の増加、研究開発やM&Aを含む企業の着実な投資拡大の好循環が生まれつつあるといって良いと思う。
かつて六重苦といわれた超円高、自由貿易協定締結の遅れ、世界一高い法人税率などの課題に関して、円安への反転、TPP大筋合意、そして税制中立という考え方が随伴措置とはいえ、法人実効税率のドイツ並みの29%台への引き下げ、地球温暖化にかかるCOP21における米国や中国等の参加した形でのプレッジ・アンド・レビュー方式への転換の実現と、これに先行してのエネルギー・ミックスをしっかり踏まえた約束草案の提出など、総理のリーダシップと担当大臣をはじめとする関係省庁の交渉力や見識の発揮によって、ビジネス環境の改善が大きく図られつつあると考えている。
目を今後に転じると、消費税の再引き上げが来年4月に控える中で、今年こそ、わが国経済を中長期の成長軌道にしっかりと乗せていく年としなければならないと痛感している。政府はアベノミクスの第二ステージとして、新三本の矢をかかげ、人口減少社会という現実に向き合った成長戦略として社会政策的ともいうべき経済政策、子育て支援、社会保障を第二、第三の矢としてかかげるとともに、名目GDP600兆円の2020年頃の達成を目指した希望を生み出す強い経済を第一の矢として位置付け、グローバル・バリューチェーンの構築、イノベーション・ナショナルシステムの構築、IoT・ビッグデータ・ロボット・人工知能による変革等を重視し、こうした課題について継続的な取組を進めようとされている。これらのいずれの課題をとってみても、政府の政策展開だけでは達成不可能であり、機械産業に横串を入れた組織体である日機連としてもこうした時代の動向を見据え、クォリティの高い活動を心がけていきたい。
昨年の賀詞交歓会において私は世界的な製造業再評価の動きについて、機械と電気・電子の機電再融合とでもいうべき潮流の中で、機、電、を横断する組織である日機連としてもこうした流れに対して積極的に取り組んでいきたいという趣旨を申し上げた。その後、政府のイニシアティブのもとでロボット新戦略が取りまとめられ、5月にはこれを受けて日機連が事務局を引き受け、IoT時代に即応したロボット新戦略の推進役としてロボット革命イニシアティブ協議会の発足をみた。その後の進展だが、226の会員の賛同を得て立ち上がったこの協議会は、現在では360を超えるところまで増加し、さらに拡大中である。各ワーキンググループも、毎回多数の企業等の参加のもと回を重ねると共に、議論も活発化し、多くの前向きの提案が会員からなされるなど、組織的なプラットフォームの形成の段階から次のステージに移行する段階を迎えつつあるように感じている。この分野の世界標準をリードすることが必須であり、そのためには会員の皆様、政府のご支援をさらにお願い申し上げる次第である。
機電再融合の流れは、機械産業の人材育成や確保の面においても注目しなければならない環境変化と認識しており、今後は日機連本体とロボット革命イニシアティブ協議会事務局が連携して政府のサポートもいただきながら、機電再融合時代の人材育成・確保のあり方について、検討を深めていきたい。また、今年は日機連本体で経産省と共にこれまで進めていたロボット大賞事業の拡充を図る年である。産業用ロボット以外の分野を含めた開発・普及の促進に向けて、積極的に取り組んでいく。
足元の景気動向は中国を始め新興諸国の景気減速など世界経済の下振れリスクが高まるなか、一進一退ともいわれているが、私どもが47の機械工業団体の協力を得て、去る11月にまとめた機械工業生産額見通しの改訂調査では、平成27年度の国内機械生産額は、当初見通しの前年度比2.6%増から0.7%情報修整の前年度比プラス3.3%という結果が出た。これは一部業種の下期を中心とした上方修正が背景となっているが、私どもとしては、この見通しが是非とも現実のものとなり、わが国経済全体としても今下期に着実な回復の動きを示すことを強く期待している。
「今年は行動をおこす年」

伊藤源嗣副会長(IHI相談役)の乾杯の発声で開宴した。
「日本の工具が世界の標準となって需要を取り組みたい」日本機械工具工業会が賀詞交歓会を開く

本間会長はあいさつの中で、「旧超硬工具協会と旧日本工具工業会が67年の歳月を経て統合を果たした。今回は統合後初めての新年を迎えたが、これから新たな歴史をつくっていきたいと願っている。会員各位のビジネスがどのように拡大をして工業会のプレゼンスが向上するのか、という課題だが、当工業会の今年度の出荷規模は4765億円であり、昨年は4553億円であるから約4.5%増の見込みだが、輸出比率をみると、33%~34%の1ポイントしか伸びがない。いわゆる内需頼みの出荷構造になっているといえるのではないか。また、日本国内の中長期的な需要構造の変化をみると、自動車メーカー各社が環境対応車の開発を進め、脱エンジン化、脱トランスミッション化が加速しており、穴加工など加工点数の減少とともに国内の切削工具の需要が減少していくと思われる。一方、世界の工具需要は約2兆円規模と推定される中で、当工業会のシェアは約20%の前半だと思われ、まだ海外には需要があるといえるだろう。この需要を取り入れるために、当工業会は、発足時の大きな目的のひとつである会員の国際化を掲げて国際委員会を新設した。会員の皆様にお役に立てる具体的な施策を順次行っていく。昨年は国産の小型ジェット機であるMRJが初飛行をした。戦後初のYS-11が飛んでから約半世紀が経ち、ものづくりに携わってきた私自身にとっても非常に感慨深いものがある。日本の航空機産業は今後さらにますます拡大していくものと期待している。航空機の機体や部品は炭素繊維強化プラスチックやインコネル材を中心とするニッケル基合金など難削材の塊であり、自動車部品と比較すると加工能率がまだまだ低いといえる。工具における技術革新が大きく残された分野である。新たな工具をJISへの規格化のためにISOの規格化を進め、この分野では日本の工具が世界の標準となって世界の需要を取り込んでいくことを期待している。今年はJIMTOF開催年になる。最新の工具を世界に発信する絶好のチャンスである。開催までに1年を切ったが、世界に評価される工具をできるだけ多く出品いただきたいと思っている」と述べた。
「企業がさまざまな価値を帯びチャンスに溢れるとき」

乾杯の発声を牛島 望 副会長(住友電気工業 常務)が行い開宴した。宴もたけなわの頃、石川則男 副会長(オーエスジー社長)が中締めを行い散会した。

「世界一のロボット利活用社会の実現へ」ロボット関連三団体が賀詞交歓会を開く

3団体を代表して津田会長があいさつをした。あいさつの概要は次のとおり。
昨今の世界経済は米国が順調な景気回復をみせる中、中国の景気減速をはじめ、新興諸国では景気回復に弱さがみられる。わが国経済は政府の経済政策効果もあり、全般的には緩やかな回復基調にある。ロボット業界においては一昨年の安倍総理のロボット革命宣言にはじまり、昨年2月に取りまとめられたロボット新戦略において明確な政策目標が示されたことは極めて大きな異議を持つ。ロボット新戦略の目標実現に向けて、5月にはロボット革命イニシアティブ協議会が設立され具体的活動がスタートしたが、このような官民を挙げた取り組みが本格的に動き出すことで、ユーザー側のロボット導入気運も大いに高まった。このような中で昨年12月に開催された国際ロボット展ではその開催規模が前回の1.5倍と過去最大となるとともに来場者数も約2割増の13万人と、大盛況の中で終了した。以上のような状況の中、わが国の昨年のロボット政策は国内出荷の二桁台の伸びと堅調な輸出を受けて対前年比6%増の6300億円となりそうである。2016年は引き続き、国内での需要増に加え、米国でのさらなる景気拡大と製造業回帰による堅調な伸び、中国での減速経済の中にあっても高い自動化投資意欲、さらに欧米におけるインダストリー4.0などIoTを通じた産業用ロボットへの関心の高まりなど今年も海外事業の拡大が期待されている。そのため、本年のロボット生産額の見通しは、昨年と同程度の伸びで6700億円と公式にまとめさせていただいた。しかしながら自動化の流れというものは非常に強く、私個人的な考えだが、7000億円という数字を期待しているところである。
次に三団体の今年の豊富等だが、まず日本ロボット工業会では中長期視点に立った業界の活性化を図る必要があるが、以下の三点を重点項目として取り組む所存である。第一は市場拡大に対する取り組みである。ロボット新戦略での世界一のロボット利活用社会の実現にあたり、当会ではロボット革命イニシアティブ協議会と連携のもと、ロボット利活用推進ワーキンググループの事務局を担当している。ロボット市場拡大に向けてその役割を積極的に進めていく。第二は産学官の連携を通じた研究開発の促進である。競争力をベースとしたグローバル市場での優位性確保や、今後の潜在市場の顕在化を図るうえでのイノベーションの加速を通じた市場の獲得・拡大が急務となっている。特に欧米先進国での技術革新に加え、新興国でのロボット技術のキャッチアップは目覚ましく、わが国としてもイノベーションの加速を図るためにも、引き続き日本ロボット学会をはじめ、関係学会および関連業界との連携に務めていく。第三は国際標準化の推進である。国際協調・協力の推進である。国際標準化活動に対して引き続き積極的に取り組む所存である。
次に製造科学センターでは昨年6月に30周年を迎えた。現在、ロボット、ファクトリーオートメーションおよびこれらを統合したものづくりの各分野における調査研究・標準化に取り組むとともに関連分野での事務局事業を実施している。ロボットでは現在ロボット革命イニシアティブ協議会の活動に参加すると共に内閣府の戦略的イノベーション創造プログラムの先端的な研究開発をテーマに参加している。今後もロボットを含むものづくり分野において次世代をさらに先取りをした産業開発のニーズに関するソリューションの調査企画、提案において会員企業、関係団体、アカデミアとともに新たな活動を展開する予定である。ファクトリーオートメーション分野では新たに今年度からは設計・製造におけるITツールに関するデータ基盤の国際標準化について関係工業会とともに取り組みを開始した。またオートメーションシステムとインテグレーションに対する国際規格であるISO-TC184の国内審議団体として活動を樹立させる予定である。その他関連分野では省エネルギー型の建設機械の導入を促進するための補助金交付事業などの事務局を務めていく。
マイクロマシンセンターの取り組みでは、当センターが活動するMEMS産業分野の国内市場規模が1.5兆円と年率2桁の伸びが見込まれるに加え、MEMSデバイスの応用普及は着実に進展している。加速度センサ、圧力センサ等多くのMEMSがスマホなど身の回りの製品にふんだんに使われており、今や各種製品の小型化・高機能化を実現するための必須デバイスとなった。さらにIoT、インダストリー4.0などのインターネット活用など新たな取り組みの中ではMEMSデバイスが大半を占める先進センサを用いたスマートセンシングは現実社会とITを連結させる重要なツールとして注目されている。
「社会課題を解決するロボット革命の実現」

「人材教育に注力したい」日本産業機械工業会が賀詞交歓会を開く

佃会長は、「今年は平穏な幕開けをするかと思ったところ株価が大幅下落し、サウジアラビアとイランとの国交断絶。いいよいよスンニ派とシーア派が正面から両派を代表する大国同士が正面からぶつかるという状況になった。挙げ句の果ては北朝鮮までが不穏な幕開けとなった。経済成長については、個々の製品、ハードの開発に加えて、今話題のロボットやIoT、ビッグデータ、artificial intelligence(AI)などの先端技術を取り入れて製品のオペレーションやメンテナンスまでを取り込んだビジネスモデルを広げて付加価値を上げ、その結果として生産性を上げるというイノベーションに取り組んでいく努力をわれわれは続けていきたいと思う。私自身、今後の日本企業最大の不安要素は人材だと考えている。教育は学校で、といって学校に任せるのではなく、インターシップの充実等々、企業が大学生や高校生により積極的に課業して、実業に関心を持って貰いたい。父や母が働いている姿に関心を持ってもらい、できれば実業の世界での野心を持って貰う、という活動が必要なのではないかと考える。老人から若者へ、という投資の配分を替えることにより将来世代への責任を果たすべきだろう。政府においては、法人実効税率20%への引き下げの前倒し、TPP交渉の大筋合意など、経済最優先の政策を強力に推進していただいている。今後ともさらなるご指導ご支援をお願いしたい」とあいさつした。
「未来への投資をしっかりと進める年に」

「自らが切り拓いていく努力が必要」日本歯車工業会が賀詞交歓会を開く

澤田会長は、「昨年当工業会は円安の恩恵を受け、収益が改善された企業が多かったのではないか。しかしながら量の拡大までは至っていないという状況である。今年は工業会としてもぜひ成長路線を牽引したい。従来は経済政策に頼っていた面もあるが、今年は自らが切り拓いていく努力が必要であろうと思っている。歯車工業会は小さな団体だが、キラリと光る活動を心がけており、日本の経済成長においても、教育というのはキーになるだろうということでギアカレッジに注力している。また技術開発においても工業会としても取り組み、新しい時代を切り拓いていこうと考えている。今年は魅力ある工業会を目指して活動していく。皆様にもぜひ参画していただき、盛り上げていきたい」とあいさつした。
「日本のものづくりは世界最高水準」、「歯車工業会は日本の歯車そのもの」
続いて、宮沢洋一 参議院議員 自由民主党税制調査会長が、あいさつの中で「日本の鋼材にいろいろ懸念されることがあると聞いた。日本のしっかりとした鋼材が使えるような状況をつくることは日本の産業にとって大切なことなの


浅川泰秀副会長(セイサ顧問)の乾杯の発声で開宴した。新規入会企業の紹介があったのち、宴たけなわのころ、猪村美之副会長(ナゴヤギア会長)の中締めで散会した。

「過去最高額を達成」日本工作機械輸入協会が賀詞交歓会を開く

あいさつに立った中川会長は、「昨年、当協会も60周年を迎えた。私自身この節目の年に会長職に就任し、今日まで務めてこられたのも皆様方の力添えがあったからと感謝を申し上げる。昨年度の工作機械の輸入通関実績は、1100億円超えを達成し、最高額の達成となった。政府による設備投資優遇策や円安による輸出の恩恵を受けた企業が設備投資をしたことと皆様方の努力の賜だと思っている。今年はいよいよJIMTOFの年。会員企業も多数出展されるが、当協会はJIMTOFの成功に向け邁進していく所存である。9月にはシカゴでIMTS2016が開催されるが当協会では今年も恒例の輸入促進ミッションを派遣する。当協会は61年目の第一歩を輸入工作機械の推進を通して、グローバル時代における日本人のものづくりを支えるため、気持ちも新たに進んでいく所存である。日本の和包丁は世界が認めているが、スイスのアーミーナイフもこれまた素晴らしいものである。われわれの輸入工作機械はスイスのアーミーナイフである。」と述べた。
新規会員4社の紹介をした。これをもって同工業会は会員数48社、賛助会員8社の計56社となった。
生産性を高めるための投資の動きが出ている

乾杯の発声はエリック・キッシュアメリカ大使館 商務部上席商務官が行った。

