破壊の科学
できたてホヤホヤの書籍をご紹介します。
非破壊検査技術の専門家である谷村康行氏が執筆した~おもしろサイエンス~「破壊の科学」(日刊工業新聞社)。
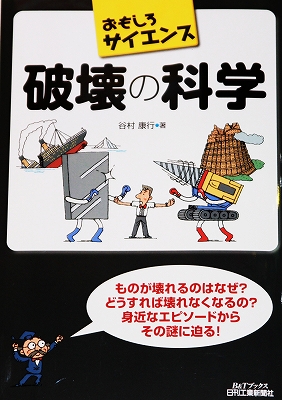
今までも谷村氏は日刊工業新聞社から「非破壊検査 基礎のきそ」など含め4冊の本を出しています。
想定する読者はおませな中学生から高校生、社会に出て間もない新人だったそうです。
今回はさらに主婦層でも読める内容となっております。ここが高いポイントです。
谷村氏は、「破壊はどうしても事故とつながり暗いイメージがありますが、科学技術としてみた場合には興味深くおもしろいことがたくさんあります。このことを伝えたくて執筆しました」とのこと。難しい内容をかみ砕いて分かりやすく説明しており、まさに専門家として実績を積んだ谷村氏だからこそ書けるのであろう充実した内容になっております。
ものが壊れるのはなぜか? どうすれば壊れなくなるのか? というテーマのもと、「ほほぅ、なるほどね!」と思わず膝を打ってしまうことがふんだんに盛り込まれています。写真や図解がたくさんあるので非常に分かりやすく、科学好きは思わず身悶えしてしまうことでしょう。
読むと、「またひとつお利口さんになってしまった」って感じでしょうか。
楽しめるうえ、とても勉強になりますよ。今まで知り得なかった謎の扉が開いたようです。
産業界で社会人を長くやってると、「今さら人に聞けないよぅ~」ってことが、ちょくちょく・・・いや、私の場合はしょっちゅうありますが、そういう方にもお勧めです。特に業界紙(誌)の記者さん、広告営業マンさんは必読の価値アリですよ。
あらっ?
今日はなぜだか本の宣伝に力が入ってしまう私ですね。
当然、理由がありますわ。おほほ。
P106~P107に不肖ながらこのわたくしめも、ちょこっとお邪魔しているワケですもの。
このようなステキな本に微力ですが貢献できて非常に嬉しく思っております。
さて、この本の大まかな筋書きは以下のとおりになっています。
●第一章 力と破壊 ―ものを壊す力とは?―
●第二章 ガラスの壊れ方 ―強化ガラスはなぜ割れにくい―
●第三章 金属は柔らかいから割れない!? ―その強さとタフさの秘密―
●第四章 さまざまな破壊とそれを防止する取り組み
この本の中のはじめに谷村氏の印象的な言葉がありました。
破壊の裏面はものづくりであり、破壊の先にあるのは創造です。破壊から悲劇の影が消える日を筆者は夢見ています―――
なんて素敵な言葉でしょうか。
この言葉にノックアウトされました。
プロフィール

業界新聞社の取締役編集長を経て、インダストリー・ジャパンを設立。製造現場は日本の底力!をスローガンに製造業専門ニュースサイト「製造現場ドットコム」を運営している産業ジャーナリスト兼フリーライターです。霞ヶ関から錦糸町まで守備範囲が広いのが特長。現場取材は数知れず。些細なことや泥臭いことに真実が隠れているのを知り、今では何より本当のことを言うのが大好き。いつも働く女性と頑張るオヤジたちの味方よ。
ブログでは取材のこぼれ話やお知らせのほか、日常のことを綴っています。
機械振興会館 記者クラブ加盟
最近のブログ投稿
- 『Mr.都市伝説 関暁夫の裏都市伝説』の新作! 「世界覇権を狙うレアメタル戦争」をテーマに那須が出演
- 【警告】「なりすまし注意」当社名を装った虚偽連絡について
- 【問い合わせ】ヘアライン加工ができる方
- 謹賀新年
- 寄席が学校に! 「THE学校寄席」
- 【お知らせ】アマダ 「2025国際ロボット展」に出展
- 【お知らせ】芝浦機械が「2025国際ロボット展」で制御技術と自動化の融合を披露
- 【お知らせ】アマダグループが「AGIC 特別イベント」 ~12月19日(金)まで開催中~
- 【お知らせ】芝浦機械×オーエスジーダイヤモンドツール「Diamond Cutting Tool Forum 2025」 を12月2日に開催!
- トライエンジニアリングで見た驚きの発想!

