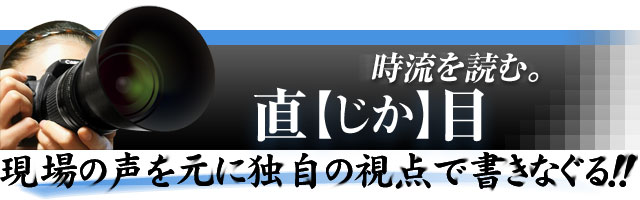
ニセモノづくりに注ぐ中国の情熱
色違いガンダムや可愛くないドラえもん、最近ではプラスチック入り偽装米が中国市場で出回っているとシンガポールメディアが報告したという、とどまるところを知らない中国のコピー商品。あの国のニセモノ開発にかける情熱は凄まじいものがある。ここまでくると、「段ボールとプラスチックが国を支えているのか?」と意地悪を言いたくなる。あっ、発泡スチロールもあったか。
製造業界でも日本の工業製品は非常に優秀だから目を付けられるのも当然だが、それにしても腹立たしい。できることなら海外の買い物客で賑わう銀座のド真ん中で宣伝カーのてっぺんに乗り「コピー商品撲滅運動」のたすきを引っさげ、ついでにバイトを雇って「経営やめますか? それとも泥棒をやめますか?」なんていうキャッチコピーのついたティッシュを道行く人々に配りたいくらいだ。
・・・とまぁ、怒ると眉間にシワが寄るので、これくらいにしましょう。
さて、これは某工作機器メーカーさんのお話なんだけど、ある加工現場からクレームの連絡が入ったことからニセモノが出回ったと発覚した。
「精度が全然出ないじゃねぇか」と、先方は大層ご立腹の様子。そりゃそうよ、良い精度を求めて品物を購入したんだもの、精度が出なきゃ怒るわよ。
高い精度に評価も高いこのメーカー、精度が出ないと言われるのは屈辱でもある。某メーカーは顧客から説明を聞いたうえで加工現場から製品を引き上げ、調べることにした。
製品が入っていた箱も自社のロゴがきちんと入ってある。印刷がちょっとおかしいとか、そんなこともない。製品の刻印もちゃんと入ってある。どこをどう見ても外見上は、おかしなところがひとつもなかった。
ところが、顧客の言うとおり精度が出ない。
「おかしいな・・・なんでだろう」
某メーカーは首をかしげた。私も以前、ここの工場や前社長さんを取材したことがあったけれど、このメーカーの品質にかける熱意は素晴らしいものがあった。世界中に流通しても自社製品に責任が持てるようきちんと製造番号もふってある。売りっぱなしにしないという意気込みを感じたものだ。
「これはおかしい」
ということで、製品を分解した某メーカー。驚きの声をあげることになる。
「あっ! これはウチのじゃない! ニセモノだっ!」
そこではじめて気付いたのだ。ある部分がちょっとヘンだった。分解してはじめて分かったという。メーカーが自社製品のコピーを見抜くまで時間がかかるくらい、そっくりだったのだ。製品の箱から刻印、なにからなにまで見事にコピーされていたらしい。
日本の工業製品は優秀なので、日本のメーカー名を出すと信用される。そこに目を付けた悪い奴。このようなことが当たり前のように起きている今日この頃。
さらに腹立たしいことは、コピー商品が見つかってバレた時の言いわけだ。
「うちらはそちらで作ってる製品よりももっといい製品をつくってやったんだ。どこが悪い」と、粗悪品をつくっておきながら悪びれることもなく、開き直ることだ。
人のモノもオレのもの、オレのモノも人のもの―――なんというジャイアニズム。
それにしても、これらのコピー商品の研究開発にかかるコストを考えると、独自の技術開発に注力してもよさそうなものなのに、創意工夫ってもんがまるでない。
・・・・というか、創意工夫が「ニセモノづくり」なんだもん。先述のプラスチック入り偽造米だって、こんな突拍子もないことを思い付くくらいなんだから、独自の開発に活用すればいいものを。とにかくあの国のニセモノづくりにかける情熱は尋常じゃない。なにかニセモノ作りに強い思い入れや美学でもあるのか。
とにかくこのコピー商品の数々、年々、匠のワザが生きてきているようで、見破るにも一苦労だ。
このような時流の中、バッタもん製品の横流しをしている輩の存在は見逃すことはできません。
製造業とトゥギャザーしようぜ!
最近、TPPに関連して農業問題がクローズアップされているが違和感を覚えることも多い。というのも、農業従事者の高齢化や農業の活性化などの問題は今に始まったことではない。本来ならばもっと以前に対処されるべき事柄ではなかったのではないか。農業政策の立ち遅れをTPP問題にすり替えているように思えてならないのだ。
テレビ番組のTPP討論会には必ずといっていいほど農水省官僚出身の東大大学院S教授が出演して反対論を述べているが、よく聞いていると、TPP問題と解決すべき農業問題をゴチャゴチャにして喋っているようだ。それなら改善すべき農業の問題点とTPPは区別して議論をしたほうが視聴者にはわかりやすいだろう。どうもテレビを見ていると工業VS農業の戦いという、低レベルな議論に流れやすいのが残念でならない。工業が利益のために農業を潰すとか、農業が経済の足を引っ張っている等、誰かを悪者にする図式も、もううんざりしてきた。
TPPについてはいろいろ議論の擦り合わせが必要であると感じている。それにはどんなメリットがあって、デメリットを“どう回避するか”が問題であり、そこのところをもっと議論してほしい。推進派と反対派に分けてデメリットばかりを突き付けても先に進まない。
ところで、見方を変えれば日本の農業にとって今が大きく発展するチャンスだと思っている。農業の弱点を強化するためにはどうしたらいいのか考える時期が来たのだと思う。それこそ保護に頼らず、日本の優れた工業技術とのコラボレーションで挽回することだってあり得る。
これは農家に限ったことではないが、どうにもならない状態であれば、悪い状態を脱する方法を考えることが先決だ。やってもいないことや、起きてもいない未来の不安にしがみつくのは良くない。今がどうにもならない状態で喘いでいるなら思い切って考え方を変えることも一案だと思っている。先が見えないことは怖いことだが、今がどうにもならないなら、今よりマシだと思えばいい。
以前にも述べたが、日本の製造業は、戦後まもなく保護貿易から自由化に転換して世界の舞台で揉まれ、結果として最高水準の技術開発力を有し経済大国の源泉になった。農業もすでに技術、品質に関しては世界のトップレベルにあるのだから、あとは生産性を高めれば国際競争に打ち勝ち日本経済の下支えができる可能性がある。
話は変わるが、ある意識調査によると、TPPの必要性について中小企業は大企業を上回って「必要だ」と答えている。中小製造企業も自立して世界に躍り出るチャンスを狙っているようだ。外で得た資金を日本に還流して、国内では最先端の製品開発や生産技術開発を行う技術創造型企業が増加する見込みもある。すでにこの形態で雇用が増えた企業も出現している。いずれにせよ日本には資源が乏しいのだから頭を使って開発するしかない。
製造業と農業が日本経済発展の車の両輪になるのは遠からずやってくるだろう。それこそ、「製造業とトゥギャザーしようぜ!」だ。
魂が抜かれそう
1月27日に財務省が発表した2010年の貿易統計速報によると、貿易黒字は前年の2.5倍の6兆7702億円と大幅に伸び、輸出の地域別はアジア向が29.0%増、中でも中国は27.9%増で過去最高を記録している。これで一応は輸出国ニッポンのメンツをかろうじて保ったと言えよう。
ところで中国のGDPが日本を抜いて世界第2位に躍り出たが、1人あたりのGDPは日本の1/10以下だ。そもそも中国は共産主義国である。そこに市場主義がどこまで浸透するのかまったく予測がつかない。中国が資本主義を目指すことは、今のところ考えにくいのだが、中国のマーケットはとてつもなく大きくて魅力的。当然、先進諸国はこのマーケットに狙いを付け、すでに熾烈な販売競争が始まっている。
一方、中国は日本の技術が欲しくてしょうがない。ご承知のとおり、日本の環境技術はトップクラス。昔の日本を辿っている中国が日本をお手本にしたいのも当然であり、すでにリサイクル技術は国家プロジェクトとして日本の技術導入に力を入れている。これは一例だが、日本の都市鉱山は中国にほとんど持って行かれている。これはなぜかというと、日本の法令上、リサイクル品が集約しにくくなっているからだ。都市鉱山は宝の山にも見えるのだが、残念なことに日本より高い料金で中国に持っていかれているのが現状のようだ。どうやら業者も「値段の高いモンに売るのは当然じゃないか」とのこと。当然だ。
20年ほど前の中国は外貨と技術が欲しいの一点張りだった。今はお金がたくさん集まったので技術に焦点を当てている。言い方が悪いが、今後も金をチラつかせて欲しい技術を奪取していくであろう。
なんとなく魂まで持っていかれるような寂しい気持ちになる。
中国に技術をどんどん売ってしまうのもいいけれど、そうなると日本に一体何が残るのか。日本の強みのひとつにサービスがあるが、サービスだけが残ったって食っていけないだろうと、ふと頭をよぎった。
サービスは日本の強み
今年はアメリカの景気回復が期待されており、明るい兆しもチラチラと見えてきた。ここで一発カマしたいところだが、国内の需要がついていかないなど課題が残っている。
年末に製造業の情勢に詳しい某氏と居酒屋でお話をしたところ、「日本はサービスと新素材だ」とのこと。私もまったく同感だった。
“売りっぱなしにしない”というキメの細かなサービスは日本の強み。最先端の設備を求める方々やそうでない方々にも“サービス”は貴重なものである。
たとえば高齢者が最新のブルーレイ付きテレビやパソコンを購入した場合、メカについていけない、ということがある。せっかく購入したのに使いこなせない。説明書が入っていてもなかなか理解できない。それがメカに疎いというもの。
私の育った田舎には安売りを全面に押し出している家電チェーン店(ここではX店)とあまり安くない地元販売店(ここではA店)がある。高齢者やメカに疎い者は、若干値段が高くても、あまり安くないA店で品物を買う。A店は昔からあるお店であり、ここ数十年の間に安さを売りにしているX店が新しく進出してきても、著しい値引きをしなかった。
田舎では若者が都会に流れる傾向があるのでメカに疎いお年頃が多く、先述のとおり、たとえば新しいブルーレイ付きテレビを購入してもイマイチ使い方が良く分からない。ところが、A店で最新テレビを購入すると、後で使い方が分からなくなってしまっても、電話一本ですぐに対応してくれる。たとえば「録画の仕方が分からない」といったことでも、家に来てくれるのだ。うちの母も最新テレビを購入した際、何度もA店に連絡をしたと聞いた。とてもアフターサービスが良いのだ。
したがって、最先端のものに腰が引ける高齢者も怖がることなく最新のものに買い替えることができる。これは田舎ならではのものだけれど、世界に当てはめてみても同じようなことが言えるのではないか。開発競争がますます熾烈化し新技術が次々と生まれてくるなかで、世界が求める多様なニーズに“売りっぱなしにしない”ということも選定の決め手になるだろう。
いずれにせよ、“かゆいところに手が届くサービス”は日本の強み。今年は日本のきめ細かなサービスをいかに世界PRするかも重要なポイントのひとつになると感じる。
沖縄はアジアゲートウェイになるか
アジア経済の成長に伴ってアジアとの物流拠点が那覇空港になりつつあるようだ。
現在、わが国産業の生産・流通拠点などはアジアへ移行していくことは避けられない状況にある。企業にとってもアジアの主要都市が那覇空港から4時間以内でスピーディに輸送できるという地理的優位性を持ち、物流にかかるコスト面やリードタイムなどにメリットが多い。
このようなことから、国内製造業も沖縄に工場を新設するのがトレンドになりそうだ。すでに進出している企業も出てきている。
日本で唯一、沖縄は亜熱帯。
たとえば精密機器・部品などは、温度・湿度に影響されやすいので、アジアの気候に合わせた技術開発をもって生産したほうがより合理的であると思われる。
これは地域を活性化し、社会貢献に繋がることは間違いない。
「この部品が足りない! このままではラインが止まるからすぐに送って欲しい」等の急を要する精密機器部品など、必要なものを素早く輸送することは以外と重要である。
このように顧客のニーズに対するクィックレスポンスは会社の信用度を増すし、国際競争に勝つ条件のひとつでもあろう。
沖縄がアジアゲートウェイになることを期待したい。
2番じゃダメなんです
ちょっと前まではマシンのトレンドといえば、高品質な多機能マシンだった。ところが、最近は海外向けの“使わない機能を省いた”シンプルマシンの売れ行きも好調だという。
昔の日本が辿った道を新興国が歩いている(小走り?)している状況にも見える。
戦後の高度成長期を支え、日本製品の国際競争力を高めたのは工作機械だ。ハイクオリティな部品や金型の数々はマザーマシンが産んだ。
今年のショッキングなニュースのひとつに28年間首位を守り続けていた日本の工作機械の生産額がドイツにも抜かれ3位に転落したというのがある。トップに躍り出たのは成長著しい中国だが、日本が決して安価な中国産との価格競争で敗北したというわけではない。一昨年9月に起こった米国の金融危機に端を発した世界同時不況の影響をモロに受け、設備投資が減少したことと国内市場の縮小が主な要因だ。
実際、アジアで人気があるのは日本製のマシンだ。価格に惹かれて中国製を購入したベトナムあたりは最近になって、すぐにガタがくる中国製のマシン離れが起きていると聞いた。いくら騙し騙し使っても限界がある。成長が見込める中で生産しても、しょっちゅう故障されてはイラついてくるのが正直なところだろう。少々値段が高くても財布が潤えば耐久性の優れた日本製のマシンに買い替え、生産能力を高めたいはずだ。
日本製の良いところは、耐久性に優れ、加工精度が長く維持できるところ。
急速な発展を遂げるアジア地域は、ここへきて情報家電や車などがグローバルに市場を駆け巡っているが、優秀な企業の多くは日本製の工作機械を使用している。
ところで、工作機械同様ものづくりの基礎をつくる金型業界も国内市場の縮小とユーザーの海外移転、想像を上回るコストダウン要求で苦しい局面に立たされている。
これらの業種が競争力を失うということは、われわれの生活を豊にするための“モノ”に陰りが出ているわけで、日本経済が弱体化していくことを意味している。このまま黙って指を咥えて新興国の追い上げを見ているわけにはいかないのだ。
現在、残念ながら国内市場の縮小は避けられないが、「売る」という観点からいくと、地球上には需要はある。先述のとおり、競争力をつけてきた海外企業が欲しているのは性能が良くクオリティの高い日本製だからだ。
このようなチャンスをモノにするためには資金も必要というもの。特に光る技術は持っているけれど、資金調達が厳しい小規模企業に対しては十分配慮して欲しいものだ。
“貧すれば鈍する”という嫌な言葉があるが、発展性が見込めたり、優秀な企業が鈍しないためにも、海外販路の開拓や、技術開発支援等に対してバックアップも必要であると強く感じている。
現状は、大・中小企業という企業規模だけの“くくり”の中で、優秀な技術を持つあるいは開発努力をしている企業と、そうでない企業がゴッタになってしまって、全体的に沈んでしまっているという現象が起きているのが残念でならない。
農業は未来産業だ!
最近、TPP(環太平洋パートナーシップ協定)の参加について議論がなされている。
自由貿易に二の足を踏んでいる問題のひとつに農業保護がある。
人口が減少している日本にとってTPP不参加は、果たして国益になるのだろうか。
輸出産業にとって、TPP参加はメリットが大きい一方、農業においては、安価な食糧が大量に入ってくることによって、“生き残り”が危惧される。農業は保護しなければならないという考えが根付いているようだ。
現在、日本の農業は内需に頼るしかないが、人口が減少する一方の日本において、国内消費ばかりに目を向けても少しも国益にならないと感じている。
日本の食べ物は非常に美味しい。米も日本酒も果物も野菜も。美味しくて、しかも安全である。世界最高水準だと言っていい。こんなに美味しくて安全な食料は世界から見てもそう滅多になく、殺菌作用の高い日本のハーブ、「シソ」だって、ヨーロッパの洒落たハーブに負けてはいない。
大量に海外から安く食糧が仕入れられて農家が困る理由のひとつに、“消費者が安価な海外モノの食材に走る”というのがある。
果たして本当にそうだろうか。
飽食の時代を経験している日本人は他国に比べ平均して食にうるさく、口が肥えている。
肥えた口はそう簡単に落とせないものだ。ちなみに個人的だが、某国の食材はいくら安くてもなんとなく怖い。同じものなら、少々高くとも美味しくて安全な方を手にするだろう。
農家はもっと自信を持ってもいい。農業に誇りを持って、若い労働力を増し、「ジャパニーズ・ブランド」を全面に押し出し、世界に売りまくることを視野に入れてもおかしくない。
そのためには、農業を法人化し、営業マンを育て、競争力を生み出していく。
農業は保護の対象ではなく、「未来産業」にする。それをバックアップするための技術は日本にたくさんあるのだ。
たとえば食材を高品質のまま安定して各国に流通させるための冷凍・冷蔵技術も優れている日本のこの優秀な技術を活用しない手はない。工業と農業が連携して世界に向かって食材を売り出す仕組みを議論してもいいんじゃないかと個人的には感じている。
技術は進歩する。良いことは誰かがマネをする。追いつかれたら終わりじゃなくて、次々と斬新なアイディアと培われた技術を持って“時流を売りぬいていく”。この考えはなにも工業に限ったことではない。農業ももっと「売る」に貪欲になってもいい。
工業も戦後、保護されていたが、その後自由化されて国際競争力をつけてきた。製造業はいつの時代も時代に翻弄されながらやってきたのだ。農業も同じように保護から脱皮して新たなチャレンジをすべきだと思っている。
日本の農家も高齢化が著しい。大改革をするチャンスだ。
JAも農業を法人化してグローバル化をするための支援・推進機関として機能をして欲しいと個人的には思っている。
希少資源問題と日本経済へのダメージ
最近、希少資源であるレアアースが大きな問題として取り上げられている。
希少資源といえば昨年6月、USTR(米通商代表部)は中国がレアメタルの輸出を制限し、国際価格の上昇を招いているとしてWTO(世界貿易機構)に提訴した。中国は国内の消費量が増加して輸出を制限したのか、政策的にタイトにしたのか謎なのだが――というより、このような問題は将来ずっとついて回る予感がする。ひょっとしたら希少資源を中国が自国で消費する可能性も十分にあり得えるのだ。
レアアース問題といえば、今年の正月早々に同じようなニュースがあった。中国はハイテク技術に欠かせないレアアースの輸出、生産の管理を強め、輸出許可枠を4年で40%も減らすと発表したのだ。40%といったら半分に近い。正月早々、嫌なニュースだと感じたのを覚えているが、今のように大きな問題にならなかったことを不思議に感じる。
これに関連することがたびたびあった。10年も15年も以前から中国に意地悪をされるたび、国内は大騒ぎした。ところが、各企業が中国以外のレアメタルの資源開発や代替開発を叫んでいたにもかかわらずこの10年間、あんまり進んでいないのを残念に感じる。ちなみに、ある資源開発の会社は、1000億円あれば、他国で開発できると以前から訴えているようだ。
中国が過去、レアメタルをタイトにするたびに、国内企業は製品の値上げ問題が浮上し、景気の悪い時に企業は、涙ぐましい賃金カット等のコスト吸収をしてきた経緯がある。
結局、これらの問題を考慮すると、当局は備蓄することしか能がなかったようにも思える。
このままいくとハイテク産業のみならず、ハイブリッド車(HV)の製造も危なくなる可能性がある。延いては日本経済へのダメージも相当なものになると感じる。すでに希少資源の在庫も怪しくなっている。
ところで、最先端技術の製品やそれらの開発に欠かせない材料はレアメタルであり、ほとんどの製造業がレアメタルを必要としているわけだが、旺盛な需要は日本だけではない。経済発展が著しいBRICsをはじめとする開発途上国もハイテク産業の成長を睨み著しく需要が拡大している。
世界中の製造業にとって必要不可欠なレアメタルの需要は、2050年までに現在確認されている埋蔵量の数倍を超えるものと予想されている。これは大変深刻な問題であり、資源リスクを回避するには「うまく使うこと」、「替わりを探すこと」だと言われている。
2007年には、内閣府、経済産業省、文部科学省、JST(科学技術振興機構)、NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)は、府省を横断して「元素戦略プロジェクト」、「希少金属代替材料プロジェクト」を国家レベルでスタートさせているが、このプロジェクトをもっと大々的にPRできないものかと思う。
すでに1950年からレアメタルの一種であるタングステンを代替する工具材料の研究は行われていたようだが、炭化チタン系サーメットを使う研究開発が当時より行われ、上記のプロジェクトでもサーメットの弱点である不均一性を追求している。
このプロジェクトはこれまでに、ジルコニウム、モリブデン、窒素などの元素を加えて混合し、高性能な熱処理で、従来よりも硬くて靱性に優れたサーメット材料を開発している。特殊な顕微鏡やコンピューターによるシミュレーションや、さまざまな設備と技術を駆使し、材料の組織をナノレベルでコントロールしたことにより、良い成果が出せるようになったようだ。
ちょうどこのプロジェクトについて1年前に書いたことがあるが、私はその後の発展がとても気になっている。
いずれにせよ、これらの希少資源の代替品の開発等は、民・官あげて“実用化”を加速すべきである。
日本の技術開発力は強い。この技術の進歩を止めないようにするには優秀な“研究者”を育てる土壌が必要だと強く感じる。
資源のない日本。企業も国も目指す道は“科学技術創造立国”しかない。

